
夏至という言葉を聞いたことがない人はいないと思いますが、いつなのか、どんなことをするのか、わかっていない人は多いかもしれません。
ここでは夏至とはどんな日のことをいうのかを解説し、2020年の夏至はいつなのかをみていきます。
また、夏至にはどんな食べ物をどんな意味で食べるのか、どのような習慣があるのかをみていきます。
夏至とはどんな行事?

夏至は「夏に至る」と書きますが、実は雨の時期真っ只中の梅雨の中にあります。
これは旧暦によって決められていたもので、今の暦で考えると少し時期がズレてしまうんですね。
旧暦では4〜6月を夏期間としており、夏至の日は5月に訪れていました。旧暦からいうと、夏に至るで夏至というのは理解しやすいですね。
また、日本には24の節気がありますが、夏至はその中でも10番目の節気とされています。
夏至の捉え方は2つ。
◼︎太陽が夏至点を通過する時刻を指している
◼︎夏至の日から小暑までの期間を指して夏至と呼ぶ
なんだか難しいですね。笑
夏至は
毎年6/21頃に設定され、冬至と比べると
5時間も差があります。
また、知られているとおり、1年の中で最も昼間が長いという特徴がありますので、ここはしっかりと抑えておきましょう!
夏至の決め方は?

正確には夏至の日は
定期法という計算式を用いて算出されます。
定期法というのは難しい計算式なので省略しますが、気になる方は調べてみてください。(すみません!)
ちなみに、今後10年間のうちほとんどが夏至は
6月21日で、
2023年のみ6月22日となっているそうです。
夏至の行事食はなに?
食事は行事を盛り上げてくれる要素の一つ。夏至にはどのようなものを食べるのが定番なのでしょうか。
夏至の反対に
冬至という日があります。これは
1年の中で最も日が短くなる日です。
冬至の日に食べるものといえばズバリ
「あずきカボチャ」
さらに、
ゆず湯に入るなど全国的に知られている習わしがあります。
一方で、実は夏至にはこのように全国的な習慣というものが見当たりません。ただし、一部の地域ではまだ夏至の習慣として残っているものがあるそうなので紹介していきますね。
| 関東地方 |
焼き餅を作って神にお供えする |
| 島根・熊本 |
団子・饅頭を作ってお供えする |
| 大阪 |
タコを食する |
| 京都府 |
和菓子(水無月)を食する |
| 愛知県 |
イチジクの田楽を食べる |
夏至の日には祭りを行う地域もあり、日本全国的には夏至という日を特別に感じている地域もあるようです。
もし、夏至の日に何か行事食を作って雰囲気を演出したいというのであれば、各地の行事食を参考にしてとり入れてみてはいかがでしょうか。
いつも何気なく過ごしている夏至の日を、特別なものに変えていけるとさらに楽しくなりそうですね。



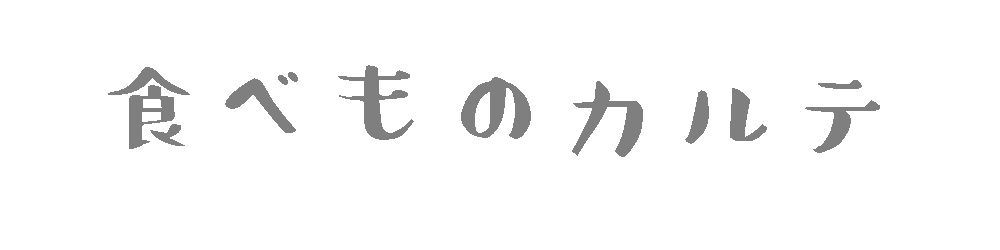



コメント